お店のコメント(スペック情報を含む場合もあり)
Amazon.co.jp
情報工学の大学生、大学院生、技術者を主な対象として、ネットワーク・システムなどの分散システムについて説明した教科書・参考書で、著者のA.S.タネンバウムはコンピュータ・ネットワークやOS設計などの教科書執筆で著名だ。
同僚と共著で2002年に発刊した『Distributed Systems: Principles and Paradigms』の翻訳が本書である。
もともと大学上級生から大学院生向けの授業の教材だったこともあり、通信機構、プロセス構成、名前づけ方式、同期手法、一貫性、フォールトトレランシィ、セキュリティ、分散オブジェクトベースシステム、分散ファイルシステム、分散ドキュメントベースシステムと続く章立ても自然で理解しやすい。
特にシステムの透過性(トランスペアレンシィ)を重視している。
これは、異機種あるいは異ソフトウエアの環境でも、個々のシステムの差異をユーザから隠して、均一なサービスを提供するために不可欠である。
翻訳では800ページを超え、中身もかなり細かく、部分的に難解であることは否めない。
もともと、分散システムは集中型のシステムに比べてずっと複雑で難しいものであった。
特にセキュリティに関する部分が難解で、システム利用者側からの視点ではなかなか十分なものにはならない。
本書はシステム開発者の視点からの記述が多いため、効率よく機能を果たす方法により重点を置いた記述となっている。
後半部では具体例を複数あげて、図9-24, 50のCORBA対DCOM、図10-54のNFS対Coda他、図11-35のWeb対ロータスノツのように比較対照表に整理して理解しやすくしている。
分散システムは、数年で最新知識の多くが陳腐化する技術進歩の速い分野であり、本書の内容は基礎的なものが多いとはいえ、引用している参考文献の大部分が20世紀のものである点を考えると、楽観もできない。
版を重ねるにしたがって、もっと分厚くなってしまうのではないかと心配な気もするが、現時点で得られる本として良い本であることは間違いない。
(有澤 誠)
内容(「BOOK」データベースより)
本書で扱う分散システムは、コンピュータとネットワークの両者を統合化するための技術であり、本来1台単独で動いていたコンピュータをネットワークで結びつけようとするものである。
それも単に回線で結びつけるものでなく、複数のコンピュータを相互に有機的に結びつけ、全体が巨大な情報システムとして動作させるものである。
このような分散システムを実現するためには、各種の新しい技術が必要となってくる。
これら技術を本書では分かり易く、かつ親切に説明している。
具体的には、まず通信、プロセス、名前つけ、同期、一貫性とレプリケーション、フォールトトレラント性、そしてセキュリティという基本的な分散技術を紹介し、その後、オブジェクトベースシステム、分散ファイルシステム、ドキュメントベースシステム、協調ベースシステムという4つのパラダイムに展開している。
商品の説明をすべて表示する
商品ジャンル
商品名
最終調査日時
2012/10/08 (Mon) 19:14:33
価格の変動(直近3回 : ¥0は未調査回)
取得日時
販売価格
ポイント
実質価格
在庫状態
2012/10/08 (Mon) 19:14:33
¥2,480
0 %
¥2,480
2012/02/26 (Sun) 23:56:01
¥2,215
0 %
¥2,215
2012/01/01 (Sun) 16:27:56
¥4,402
0 %
¥4,402
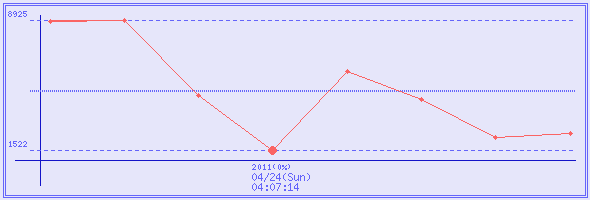
サイト内キーワード検索
商品名の検索は通常の商品検索ボックスで。
コメントやスペックなどから検索したい場合はこちらから。
コメントやスペックなどから検索したい場合はこちらから。
広告


![【クリックでお店のこの商品のページへ】分散システム―原理とパラダイム [単行本]](http://ec2.images-amazon.com/images/I/51BQHA956FL._SL500_BO2,204,203,200_PIsitb-dp-500-arrow,TopRight,45,-64_OU09_AA240_SH20_.jpg)


